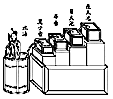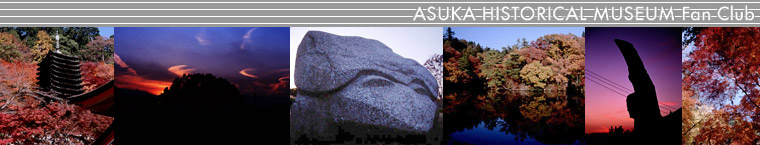
|
|||||||||
 北溝の発掘  現地説明会 |
10月24日土曜日、中心の穴の北西付近で溝の埋土を掘ると、腐蝕土の中より、細長い銅製の管が、溝方向の南北に横たわっていることが明らかになった。あまりにも予想外のものが出現したので、一瞬、判断に苦しむほどであった。しかし、銅管を確認するために、急いで全部の溝を掘るのは危険であったので、現地で写真を撮影し、現状のまま、一旦埋め戻した。また、中央の柱位置の穴が大きいところから、塔の心礎状のものが想定された。あるいは、天上に聳える高殿があったのであろうか。夕刻になると、発掘現場の状況に話がはずみ、調査員達は夢をふくらませた。日わく、小墾田宮兵庫説、天武殯宮説、饗宴場説、仏塔説、池中楼閣殿舎説など、総柱とその中心の大穴から考えられる建物についで百家争鳴であった。 11月14日の午後、石神遺跡と合わせて、現地説明会を催した。約280人の人々が集った。しかし、人々の関心は、昭和11年以来の調査となった石神遺跡に向いていたといえよう。 |
| 現地説明会の翌々日より、基壇の築成状況を見るために、基壇を裁ち割って、土層を観察する調査に移った。これは発掘調査の最終段階にあたる。まず、基壇北側の玉石が少し抜かれた場所を選んで試掘拡が堀られた。先に見つかっていた銅管の延長と思われるところで、この基壇の下に銅管が配管されていることが確認できた。この銅管には粘土がつまっていたところから、少量の水が流れていたと考えられた。とすると、地下の鋼管には、導水のからくりがあると思われた。この時、すぐ東の石神で発掘していたこともあって、『日本書紀』斉明6年(660)の須弥山石のことが調査者の脳裏をかすめた。と同時に、その記事のすぐ前にある、中大兄皇子の造った漏刻だとしたら、木樋や銅管は水時計の装置の一部になるのかもしれないと思われるようになり、これは重大なことになったと胸がおどった。 数日後、引き続いて基壇上の東側から木樋が出土するに及んで、基壇上面の陥没しているところでは、木樋が埋まっているとの確信を得るようになった。また、中央の大穴には、大石の埋まっていることが判明し、その上に漆の痕跡のあることが判った。はたして、これまで想像もしなかった水の配水路がめぐる水時計であろうか。仮にそうだとすれば、これまで飛鳥の研究のなかで考えたこともない、想像を絶する遺跡になるのではないかと推測されることになった。 連日、現場から引き上げた夕方になると、異なる分野の研究者も加わり、調査データをもとにして激論がかわされた。昼間の調査で、疲労は極限に達していたが、新しい事実を前にして興奮気味で、時間がたつのも忘れて討論が続いた。新しい成果がまとまると、時には乾杯をあげることもあった。こうして、調査は次第に水時計に焦点がしぼられていった。当初は、『古事類苑』や『漢和大辞典』などによって、水時計の構造を知り、その後、唐代の水時計として知られる呂才の図をもとにして検討を進めたが、あの基壇上に階段状の漆箱があったのかどうかが問題であった。 |
|
 銅管の発掘  漆塗木箱の精査  漆塗木箱の精査  礎石の発掘 |
一方、同時に発掘調査を進めていた石神遺跡の進行が、やや遅れ気味になってきていたので、水落遺跡の調査を一時中断して、総力を石神遺跡に向けることになった。ここでの3週間の中断は、結果として、大変貴重な時間となった。検討したことを現場で確認したい心の高ぶりを押えて、漏刻の史料を収集した。とくに、東洋科学史の研究者として知られた、オッグスフォード大学のJ.二一ダムの『中国の科学と文明』を見る機会があったのは幸であった。また、天文、暦法をはしめ、中国科学史の研究者として有名な藪内清氏のところへ教えを受けにいくとともに、同じ研究者の京都大学人文科学研究所東洋部教授の山田慶児氏に現地で指導を受け、かなり具体的な漏刻像が調査員の知識のなかに構築されることになった。この時点で、楼閣状の建物は占星台を兼ねた施設であるとの考えにまとまりつつあった。 石神遺跡の発掘が一段落した12月14日、しぐれ雪の中、調査班は水落遺跡に戻ってきた。「鋼管」、「木樋」、「大石上の漆塗木箱」の3つのキーワードが果して時計として一つにまとまるのだろうか。期待と不安が交錯するなかで、鋼管が埋まっていると思われる溝を掘り進めた。銅管は木樋で被覆され、予想どおり南北に一直線に埋設されており、北は石敷溝の下を通り、旧校含の方へと延ぴていた。また、東西に走る木樋を追跡すると、基壇中央で桝に流れ込み、そこからさらに北へ延ぴていた。桝の手前にはサイフォンの役をするラッパ栽銅管があった。おそらく、西流する水が桝の堰板で止められ、導水元との水位の差を利用して、サイフォンで上へのばったのであろう。もう一本の木樋は、西へ通過している。その後、時間をかけ、大石にこぴりついた漆の被膜を丹念に追跡した。大石には長方形の窒みが彫られており、ここに、漆塗の木箱があったことが判った。さらに、その北半に、もう一まわり小さい漆塗の箱の痕跡が認められ、この箱が呂才の漏刻の最下層になる水海にあたると思われた。脆弱な漆膜の発掘は、緻密な慎重さが要求されるもので、漆塗木箱の精査に数日間かかりきりになった。 これと同時に、建築学的にも、全く予期しなかったことが明らかになった。前回の調査以来、柱穴は礎石を抜き取った時の穴と考えられてきたが、掘方が急傾斜で下るところが不自然であり、また、深さも1m近くあり、これまでの調査経験では理解できないところも多かった。そこで、埋土の土層を見るため、完全に掘り下げたところ、穴の底には円形柱座を彫り込んだ礎石が据えられていた。これは、まさに小形の心礎である。しかも、この地中に埋まる礎石は、お互いをやや小形の花崗岩河原石でつないでいた。さらに、礎石の外側に向けても、放射状に河原石でおさえていた。このような基壇築成途中に礎石を埋め込む例は、初出土の資料であるし、特異な礎石による建物は、漏刻台説を強く裏付けることになった。「銅管」と「大穴から見つかった漆塗木箱」から発展した推察は、こうして証明されたのである。ただ、細長い銅管は水時計のための配管ではなく、水を利用する他の施設の一部分と思われた。 |
| 12月17日午後、旧小学校含で、水時計の発掘成果について報導関係者に発表した。これまでの発掘調査の発表は、遺跡、遺物が語り、説明を要しない場合もあったが、今回は、かなり詳細な説明を必要とする遺跡となった。翌日、フェンスで囲まれた遺跡の周囲には、多くの見学者がつめかけ、空には取材のヘリコプターやセスナ機が飛ぴかった。方形基壇上の調査員達は、衆人看視のボクシングのリング上で発掘をしているような具合となった。こんな中でも、基壇のチェックは順調に進み、ラッパ状銅管の取り上げや漆塗木箱の細部の調査ができた。新聞、テレビをはしめ、マスコミは、連日、水時計の特集記事を組んだ。数日後、現場の飛鳥の御婦人達が調査の成功を祝ってぜんざいを作ってくれた。年の瀬もおしせまった12月26日、こうして「飛鳥の水時計」の発掘は完了した。 あわただしく年が明けると、土中でやっとつきとめた時計の構造を実験的に証明する必要があった。漆箱の容積を復原し、これをもとにして、地上で階段状に4層の水槽と箭を立てるとどうなるか、発掘スタッフの資料をもとに、科学史、流体力学等の研究者も加わり、さまざまな角度から検討された。こうしたデータに基き、国立民族学博物館の協力を得て、コンピュータによる水の流れと箭の動きを解析したものができあがった。また、京都大学人文料学研究所で研究会も行なわれた。さらに、各方面の援助のもとに実大の模型を作る機会があった。一方、スイスの時計会社により日本最古の水時計の遺構模型が飛鳥資料館に寄贈されることになり、地下の構造を理解すべく光ファイバーによって水の流れを示した模型が完成した。漆の断片になっていた漆箱は、原寸大の水槽を作り元の位置に漆留めにして修理された。また、銅管は、顕微鏡観察の結果、銀鑞で接着していることが明らかになった。 昭和57年春、奈良国立文化財研究所は、東京と大阪で「飛鳥の水時計」の公開講演会を催した。両会場とも、多数の古代史ファンで満員となった。 |
|
 Copyright (c) 1995 ASUKA HISTORICAL MUSEUM All Rights Reserved. Copyright (c) 1995 ASUKA HISTORICAL MUSEUM All Rights Reserved.Any request to kakiya@lint.ne.jp Authoring: Yasuhito Kakiya [K@KID'S] |