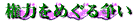伝続的な大豪族・物部氏は、新輿の実力者に立場を脅かざれるという危機感から、当然のように蘇我氏と対立していた。権力の座をめぐる争いは、外国から渡ってきた新しい神をどう受け入れるのかという間題をとおして表面化する。仏教を国の正式な宗教としようという蘇我氏と、物部氏を旗頭とするこれに反対の立場の旧勢力とは、ことあるごとに小競り合いを繰り返してきた。
そして585年、敏達天皇の死で事態は波乱に向かって動きはじめる。一応は、大臣馬子の狙い通り堅塩媛と舒明の子供・大兄皇子が即位して用明天皇となった。しかし、これに不満をもった用明の異母兄弟・穴穂部皇子は王位を窺い、これを後押しする大連物部守屋は蘇我氏との軍事的対決色を強めていく。暴行未遂事件、暗殺事件、呪誼事件が相続き、両豪族の緊迫した呪み合いが続く中、即位4年目の用明がこの世を去り、第一の破局が訪れる。
物部氏が戦の準備を整えている間に、馬子は先手を打って、まず争いの主役とも言える大穂部皇子を殺してしまう。守屋の戴くべき大義名分を取り除いた馬子は、故敏達天皇の妃・炊屋姫(後の椎古天皇)と諮って、蘇我系の皇族・蘇我系の豪族の勢力を結集する。守勢にまわらざるをえなくなった守屋は渋川の邸宅で必死の抵抗をこころみるが、結局は馬子の攻撃をささえきれず戦死、物部氏は滅亡する。守屋の屋敷のあった渋川は河内国渋川郡、現在の大阪府八尾市にあたるという。
最大の政敵・物部氏を倒した蘇我氏は、穴穂部と同じ母をもつ弟・小姉君と欽明の子供・泊瀬部皇子を崇峻天皇とした。事態は落ち着いたかに見え、蘇我氏の長はまさにキング・ノーカーと呼ぶにふさわしい地位を占めて外交・内政の主導権を握る。ところが、崇峻天皇は大臣の存在を煙たがり、その力を取り除こうとする動きをみせる。
馬子は592年、朝廷内の最大にして唯一の対立者となった天皇を殺してしまう。天皇暗殺を、有無をいわせない既成事実として王族・諸臣につきつけられるほど、この時点ですでに馬子の支配体制が揺るぎないものとなっていたとも言える。
こうして第一の披局は、蘇我氏が結束して対立勢力を一掃するかたちで決着を見、推古天皇の36年に亙る安定した時代がはじまる。推古は飛鳥豊浦に最初の宮殿を置いた。この地はもともとは稲目の屋敷があった場所で、後には馬子の子供・蝦夷が豊浦大臣と呼ばれている。天皇と蘇我氏との強い絆を読み取ることができる。
馬子は、引き続き大臣として朝廷の中枢に腰を据え、境部臣、田中臣、石川臣といった稲目の息子たちも、それぞれが政権に参画する大貴族となっていく。天皇の後継者にも蘇我氏とつながりの深い聖徳太子がすえられた。蘇我氏を中軸とした政権は、中国までを視野にいれた積極的な外交、屯倉の整備と治水事業などの農業振興策を通じての朝廷の経済力の強化、そして仏教を中心とする先進諸国の例にならった文化政策をおしすすめる。まさに蘇我氏の黄金時代が実現したと言うことができるのではないだろうか。
しかし、何事にも終りはある。馬子は推古34年(626)に死に、二年後には推古もあの世へと旅だつ。推古の後を継ぐはずだった聖徳大子もすでに早世しており、ぷたたぴ大騒動がもちあがる。
付け加えておけば、馬子は76才で死んだといわれる。推古は治世の36年に75才で亡っている。叔父と姪といっても二人の歳の差は三つほどしかなかった。物部守屋を討って蘇我氏の時代の幕が開いたとき、推古は35才ぐらい、馬子は40才すこし前、聖徳大子は15・6才だったことになる。
|